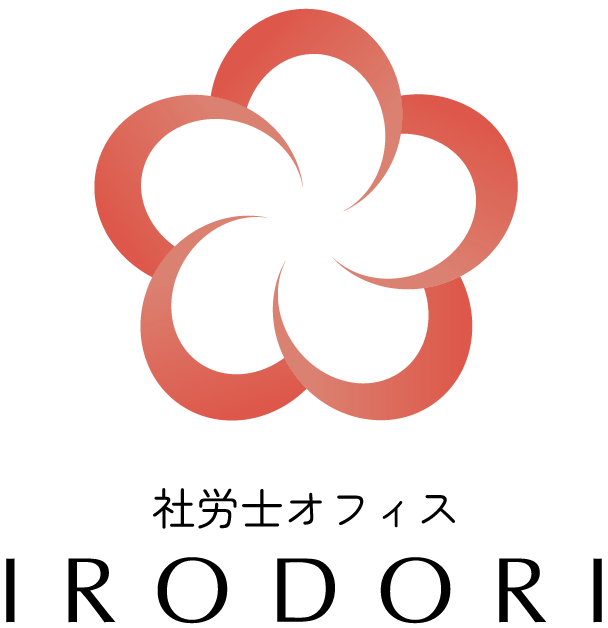労務管理
労務管理は、コンプライアンスの強化や働き方改革関連法の施行により、その重要性が高まっています。
とはいえ、労務管理の内容は幅広く複雑で、実際の現場では一律のルールでは対応しきれない場面も多くあります。
社労士オフィスIRODORIでは、企業様のニーズに合わせた労務管理のサポートを提供しています。
例えば、以下のサービスを通じて、労務管理を強化し、従業員の満足度向上を目指します。

労働条件通知書(雇用契約書)
従業員を雇用する際には、労働基準法に基づき「労働条件通知書」を作成し、従業員に交付等することが義務付けられています。
「労働条件通知書」には、賃金、労働時間、休日などの法定項目を記載する必要があります。
これは、給与・勤務時間・休日など、働く上で大切なルールを書面で明確にするものです。
◆たとえば…
「契約期間は〇年〇月〇日~1年間」「勤務時間は朝9時から夕方6時まで」「基本給20万円、+固定残業手当5万円」など、具体的に記載しておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
また、労働条件を明確にすることで、後々の行き違いやトラブルを防ぐことにつながります。
特に業務内容や就業時間、賃金についてのトラブルが起きやすく、双方で確認の意味も含めてきっちりと書面等を作成しておく事がトラブル防止につながります。

社労士オフィスIRODORIでは作成時に紛争予防に必要なポイントなどもアドバイスさせていただきます。
ご要望に応じてひな形もお渡しさせていただいております。
労働時間の管理、残業
「労働時間の管理」や「残業代の支払い」は、労務管理において特にトラブルが起こりやすいポイントのひとつです。
残業代の不払い・計算ミス・あいまいな運用は、従業員との信頼関係を損なうだけでなく、法的なリスクにもつながります。
実際のトラブルの多くは、明確なルールや運用がされていないことが原因です。
最近では「フレックスタイム制」などの柔軟な働き方を導入する企業が増えている一方で、「固定残業代制度」など、給与体系に特徴のある制度を取り入れるケースもあります。
これらは正しく導入・運用しなければ逆にリスクとなってしまいます。適切に導入することで、法令を遵守しつつ、残業を抑える働き方の設計は可能です。
ただ、これらを適切に導入し、運用できている企業は多くありません。

社労士オフィスIRODORIでは、企業の状況を丁寧にヒアリングしながら、無理のない制度設計と、実態に合った労働時間管理の方法をアドバイスさせていただきます。
適正な労働時間の管理は、従業員の安心と企業のリスク回避、どちらにもつながります。
就業規則
労働者が10人以上の事業場では、「就業規則」を作成し、労働基準監督署に届け出をすることが義務付けられています。
これは会社の「ルールブック」とも言えるもので、出勤時間・休暇・服務規律・懲戒の基準などが記載されています。
たとえば、「遅刻が3回続いた場合は注意喚起を行う」「無断欠勤が5日続いた場合は懲戒の対象とする」など、具体的なルールを定めておくことで、問題発生時の対応にもブレが生じにくくなります。
◆たとえば…
服務規律には、最近トラブルの多いSNSの取り扱いについても、具体的に定めておくことが有効です。
一例を挙げると、 「業務上知り得た内容や情報(業務内容、事業所に関すること、社員個人に関することなど)をSNS等に投稿してはならない。ただし、事前に会社の許可を得た場合はこの限りではない(さらに続く・・・)」
といったルールを明記しておくことで、問題が発生した際にも対応方針にブレが生じにくくなります。
企業側からすれば「それくらいは常識」と思う内容でも、従業員とのあいだに認識のずれがあることは少なくありません。
こうしたずれを事前に防ぐことも、就業規則の大切な役割のひとつです。
ただし、「作成と届け出はしたけれど、従業員がその存在を知らなかった」という状態では意味がありません。
就業規則は従業員に周知されてこそ効力を発揮します。
また、トラブル発生時に、就業規則の内容を会社の都合の良いように解釈し運用すると、トラブルの原因となることがあります。冷静かつ客観的に判断することが必要です。

社労士オフィスIRODORIでは、就業規則に沿った矛盾のない対応を行い、極力トラブルに発展しないような就業規則の運用をアドバイスしています。企業が安心して労務管理を行えるよう、専門的な知識と経験を活かしてサポートいたします。
※就業規則は非常に重要な役割を果たしますので、詳細は「就業規則」のページをご参照ください。
年次有給休暇
「有給休暇って何日取れるの?」「いつまで有効なの?」「同僚や上司に気兼ねして休みにくい」「会社に勝手に消化された」など、有給休暇に関する従業員からの問い合わせは非常に多く、付与日数や残日数、取得義務の日数、時効による失効日数など、細かな点まで把握して対応する必要があります。
2019年4月1日から施行の働き方改革関連法により「年5日の有給休暇取得が義務化」されました。
このルールを正しく理解していないまま放置してしまうと、トラブルに発展する可能性もあります。
しかし、これらを企業の担当者や社長が社内だけで完全に理解し、正確に対応するのは難しいのが現実です。

社労士オフィスIRODORIでは、企業様からの有給休暇に関するお問い合わせにもスムーズに対応できるよう、分かりやすく丁寧にアドバイスをいたします。
また、ご要望に応じて有給休暇の管理業務も承っております。
付与忘れや消化義務の未対応、取得日数の過不足などのトラブルを未然に防ぎ、安心して運用いただける体制づくりをサポートいたします。
解雇トラブル回避
解雇は、従業員の生活に大きな影響を与える重大な決定です。
遅刻の多い社員に、上司が「勤務態度が悪いから、もう来なくていい」と発言したり、業績不振を理由に社員を突然解雇した、などと安易な判断で進めてしまうと、「不当解雇」として争いに発展するケースも少なくありません。実際に裁判などでは、会社側が不利になることも多く見られます。
それはつまり、「ちょっとした理由では解雇は認められない」ということ。
解雇が有効とされるには、“社会通念上相当”と判断される必要があります。
ただ、この“社会通念上相当”という基準は、誰にでも明確にわかるものではなく、判断が分かれることもあります。
だからこそ、感情的にならず、冷静かつ客観的に状況を見極めることが大切です。
解雇を検討する際には、トラブルに発展しないよう、事前に専門家に相談しながら慎重に進めることをおすすめします。

社労士オフィスIRODORIでは、状況を丁寧におうかがいしながら、適切な対応策を一緒に考えていきます。「どう伝えるか」「何を整えておくべきか」といった実務面も含めご相談対応させていただきます。
お問い合わせ
CONTACT