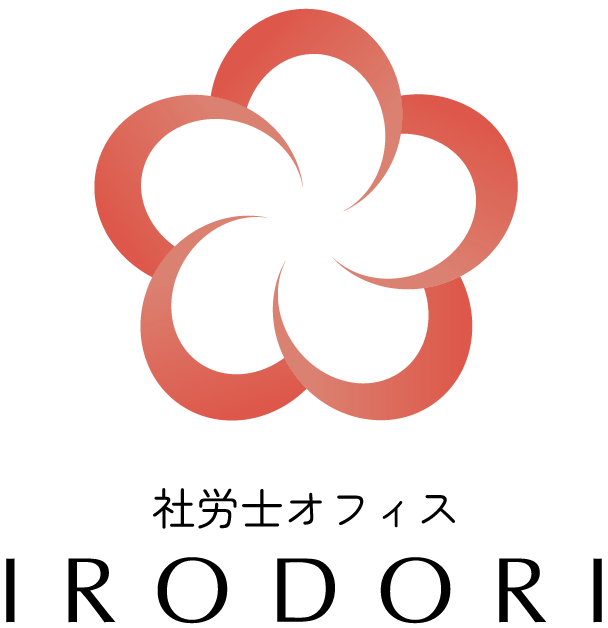就業規則
就業規則は、企業と働く人が安心して仕事に取り組むための「ルールブック」です。
就業規則の作成は、作成実績多数の社労士オフィスIRODORIにお任せください。
就業規則が会社を守る
就業規則がなければ、「何がよくて、何がだめなのか」という線引きが曖昧になり、トラブルが起きたときに企業としての対応が非常に難しくなります。
「まだ従業員数が少ないから」「今のところ問題がないから」と後回しにされがちですが、就業規則は、企業と従業員が安心して働ける環境を支える土台です。
就業規則は、労務トラブルの予防・対策の為に、必須アイテムです。万が一紛争に発展した場合、就業規則がなければ話し合いの土俵にすら上がれないこともあります。
就業規則には、会社としてのルールを明確にし、従業員の権利を保障すると同時に、企業側の求める義務も定める必要があります。
一方的な主張や不当な内容ではなく、バランスの取れた内容であることが重要です。そのバランスをとるには経験と知識が欠かせません。
当事務所では就業規則作成のご依頼をたくさんいただいております。
安心してお任せください。
◆よく見られる就業規則の整備のきっかけや理由
- 従業員が増えてきたから、ルールを明確にしておきたい。
- 昔作ったまま何も手を付けていない、内容が実態と異なっている。
- 社内の秩序を守って、頑張っている従業員を守りたい
- トラブルが起きないように、企業の考え方を示したルールを作っておきたい
- 休職者対応をしておきたい

就業規則が無い又は不備がある場合のトラブル例
残業や休日労働の申請方法が決まっておらず、無断残業や申告漏れが発生してトラブルに
就業規則に「残業は事前申請・承認制とする」などのルールを定めておくことで、無断残業や過剰な残業を防止し、残業代の管理・支払いも適正に行えます。また、労働時間を適正に把握する必要がある企業側としても、労務管理のリスクを軽減できます。
休職・復職対応でトラブルに発展する
従業員のメンタル不調などのご相談は急増しております。休職についてのルール作りや運用は簡単ではありません。休職期間をどれくらいで設定するのか、復職についてはどう取り扱うのか等を就業規則に記載しておくことが重要です。
問題行動を起こした社員に懲戒処分をしたのに「ルールがない」と反発される
原則、就業規則がなければ懲戒処分は出来ません。しっかりと就業規則の中で記載しておく必要があります。
問題社員への対応ができず、組織の士気が下がり、退職者がでる
就業規則は、真面目に働いている従業員を守るためにも重要な役割を果たします。労働者であれば当然守るべきことを服務規律等で記載し、それが実行できない場合の処分を就業規則に記載します。
廃止になった手当の記載が残っている
就業規則から削除していない場合は、その通りに支払う必要があるので変更対応が必要となります。
時間外手当などの割増率に不備がある
時間外手当は法律で決まっている最低限の割増率がありますが、それ以上の割増率を設定している例があります。理由をお尋ねしても不明であることが多く、実態に合わせた変更が必要となります。
ハラスメント(パワハラ・セクハラ等)への対応ルールが無く、どう対応すべきか分からない。
就業規則に「ハラスメントの定義」と「会社の対応方針」を明記しておくことで、ルールに沿った適切な対応が可能になります。
令和4年4月からは、パワーハラスメント防止措置が全事業所に義務化され、事業主には「加害者に対して厳正に対処する方針や具体的な対応内容を、就業規則などに記載すること」が義務付けられています。
就業規則を整えておくことで、従業員が安心して働ける環境づくりにつながり、会社を守ることにもなります。
副業やテレワークのルールが整備されておらず、情報漏えい等が心配
就業規則で副業やテレワークに関するルールを明確にすることで、情報漏えいなどのリスクにそなえます。あらかじめルールを整備しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、柔軟な働き方にも対応できる体制が整います。
有給休暇を年に5日使用させなければならないが、なかなか取得がすすまない
就業規則に「計画的付与制度の導入」や「有給取得の申請方法・時季指定のルール」などを定めておくことで、計画的かつ確実に取得を促すことができます。計画的付与制度を導入する場合は別途労使協定の締結も必要となります。
育児・介護休業などの制度の取り扱いが不明確で、トラブルが起きやすいと聞きます
育児介護休業法は法改正が頻繁にあるので、就業規則を常に最新の状態にアップデートすることが必要です。
また、従業員に制度内容や申請手続きの周知を徹底することで、誤解やトラブルを防ぎ、スムーズな取得を促せます。
定年や再雇用に関する規定が無く、シニア社員とのトラブルに
定年の規定がない場合、一定の年齢に達したからといって自動的に退職させることはできません。現行の法律では、定年は60歳以上と定められており、65歳までの雇用機会の確保(継続雇用制度や再雇用制度など)が事業主に義務付けられています。
また、会社の実態に合っていない場合(例;定年が65歳なのに、70歳の従業員を入社させている、等)もトラブルになりやすいので、企業ごとの実態に合わせた規定づくりが重要となる部分です。
SNSの利用ルールが明確でなく、情報漏えいや企業イメージの低下に…
従業員が社内の情報や顧客に関する内容を無断でSNSに投稿したことで、情報漏えいやクレームに発展するケースもあります。就業規則でSNSの使用に関するルールや注意点を明文化しておくことで、思わぬ炎上や信用失墜といったリスクを回避しやすくなります。
異動(転勤、配置転換、業務内容の変更等)を巡って紛争になる…
企業には、異動を命じる権限があります。そのため、就業規則に異動の可能性を明記しておくことが重要です。
こうした記載がない場合や、個別に同意を得ていない状況で一方的に異動を命じた場合、違法な異動と判断され、無効とされたり損害賠償請求を受けるリスクもあります。
作成手順
打ち合わせ(1回目)
当事務所からの質問事項にご回答ください。
就業規則の作成(所要期間:約2ヶ月)
打ち合わせの内容を基に、当方で就業規則の作成作業をいたします。
打ち合わせ(2回目)
作成した就業規則をご確認いただき、修正・改良のご要望をお伺いいたします。
就業規則の修正・改良(所要期間:約1週間~1ヶ月)
打ち合わせの内容を基に、就業規則の修正・改良作業をいたします。
最終確認
最終確認をしていただき、問題なければ完成です。 データにて納品をさせていただきます。
お問い合わせ
CONTACT