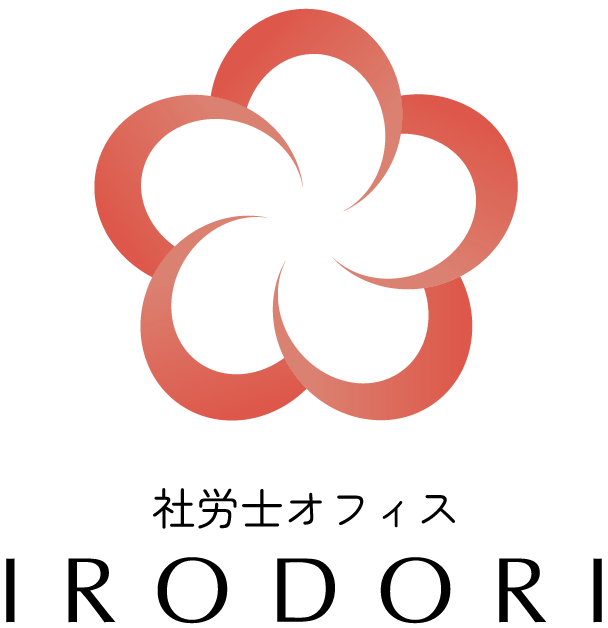育児休業・介護休業
近年、育児休業や介護休業に関する法改正が頻繁に行われており、その内容も非常に複雑です。
「いつ、何を、どうすればいいのか分かりづらい」と感じる企業様も少なくありません。
改正が続く中で、企業側が適切に対応するのは難しく、正直なところ、専門家でも困惑することがあります。
「どこが変わったのか」「どのタイミングで新しいルールを適用するべきか」こうした疑問は、
現場で対応している企業様にとっても大きな悩みの種です。
さらに、改正された内容を就業規則に反映させることや、従業員への適切な案内を行うことも求められます。
このような手続きや運用の変更を、企業側が完全に理解し、漏れなく実行するには、
時間と労力がかかり、注意深く管理しないとトラブルに繋がりかねません。

そのため、専門家である社労士にお任せいただければ、
最新の法改正に基づいて、スムーズに手続きを進めることができます。

社労士オフィスIRODORIでは、
- 育児・介護休業の取得に関する手続きサポート
- 育児休業給付金・介護休業給付金の申請支援
- 制度に合った社内ルール(就業規則や書式)の整備
- 社内説明のポイントや、現場での対応のアドバイス
など、実務に即した形でサポートしています。
「制度はあるけど、うまく使えていない」「従業員が安心して休める環境を整えたい」
そんな企業様は、ぜひ一度ご相談ください。制度の仕組みと実務の両面から、丁寧にサポートいたします。
社労士オフィスIRODORIでは、法改正情報を常にキャッチアップし、企業様が新しいルールに沿って対応できるよう、しっかりとサポートしています。最新の制度に即した、安心のサポートをぜひご活用ください。

育児・介護休業制度の基礎と企業対応のポイント
近年、仕事と家庭の両立を支援する法制度が大きく進化しています。
「育児休業」や「介護休業」は、従業員のライフイベントを支える制度であると同時に、企業にとっても人材定着・職場の安心感づくりに欠かせないものとなっています。
(※下記は分かりやすい説明を意識し、法律上の語句を使用していなかったり、詳細説明を省略している部分がありますのでご留意ください。)
育児休業とは
育児休業とは、原則として子どもが1歳になるまで(一定の場合は最長2歳まで)、仕事をお休みできる制度です。
雇用保険の被保険者で一定の要件を満たす場合、従業員には「育児休業給付金」が支給されます。
育児休業給付金の概要(※雇用保険加入者が対象)
- 育休開始から180日目まで:賃金の67%
- 181日目以降:賃金の50%
※実際の手取りは社会保険料等が免除されるため、もう少し高くなります。
男性の育児休業も進んでいます(パパ育休)
2022年4年から導入された「出生時育児休業(通称:産後パパ育休)」では、子の出生後8週間以内に最大4週間(分割取得可)の育休取得が可能です。
また、2025年4月以降は、従業員300人超1,000人以下の企業にも、男性育休の取得状況の公表が義務化されました。
これにより、企業の姿勢がより社会から問われるようになります。
- 育休中には「出生時育児休業給付金」が支給されます(賃金の67%相当)。
- さらに、2025年4月からは「出生後休業支援給付金」という新たな支援制度も開始されました。
→ 育児休業を取得した男女両方に対して、収入の上乗せ支援が行われる制度です。
現場でよくある相談と企業対応
企業側が正しい制度理解と適切な対応をすることで、従業員の不安を減らし、安心して職場復帰できる環境づくりにつながります。
- 「保育園に入れず、職場復帰が難しい。退職しなければいけませんか?」
→育休の延長制度を案内し、退職を急がせない配慮が可能です。 - 「夫婦で同時に育休を取れると聞いたのですが、給付金も増えるのでしょうか?」
→育休の取得時期によっては、給付金の調整や出生後休業支援給付金の対象となるケースもあります。
介護休業の概要
高齢化が進む中、介護による離職を防ぐために設けられた制度です。
従業員が家族を介護する必要があるとき、一定の条件下で休業を取得できます。
- 対象:要介護状態の対象家族を介護する必要がある労働者(日々雇用を除く)
- 対象家族:配偶者、父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫
- 取得可能日数:対象家族1人につき、最大3回まで、通算93日まで取得可
介護休業給付金の概要(※雇用保険加入者が対象)
- 賃金の 67%
社労士からのひとこと
育児・介護休業は、「権利として存在する」だけでなく、企業としてどう向き合うかが問われる時代になっています。
制度をきちんと理解し、運用面でのトラブルを防ぐためにも、社内ルールの整備や就業規則の見直しがカギとなります。
「育児休業の延長申請は誰が対応?」「給付金の手続きはいつ・どのように?」といった細かな疑問にも対応できる体制づくりを、ぜひご検討ください。
お問い合わせ
CONTACT