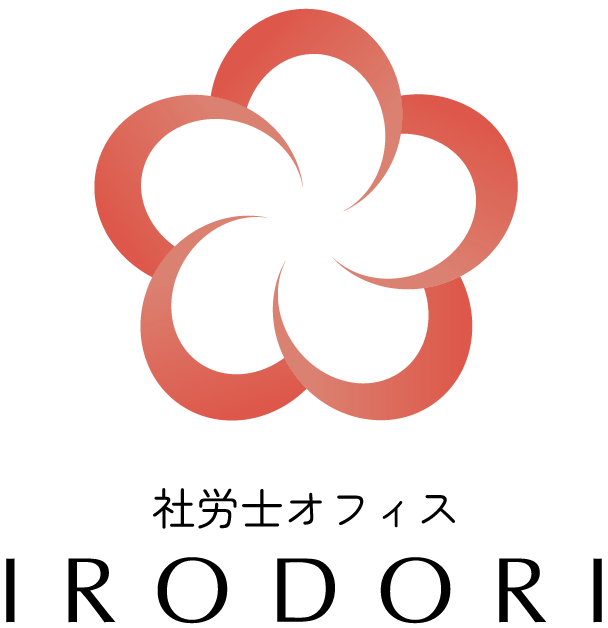給与計算
給与計算は、一見毎月のルーティン作業…
そう思われがちですが、実は多くの企業にとってトラブルの火種なりやすい業務です。
たとえば・・・
- 残業代の計算ミス
- 控除額(社会保険料・住民税等)の誤り
- 法改正や保険料率の変更への未対応
こうした見落としが、従業員との信頼関係を損ね、労務トラブルや行政指導、追加徴収を受けるリスクになることもあります。
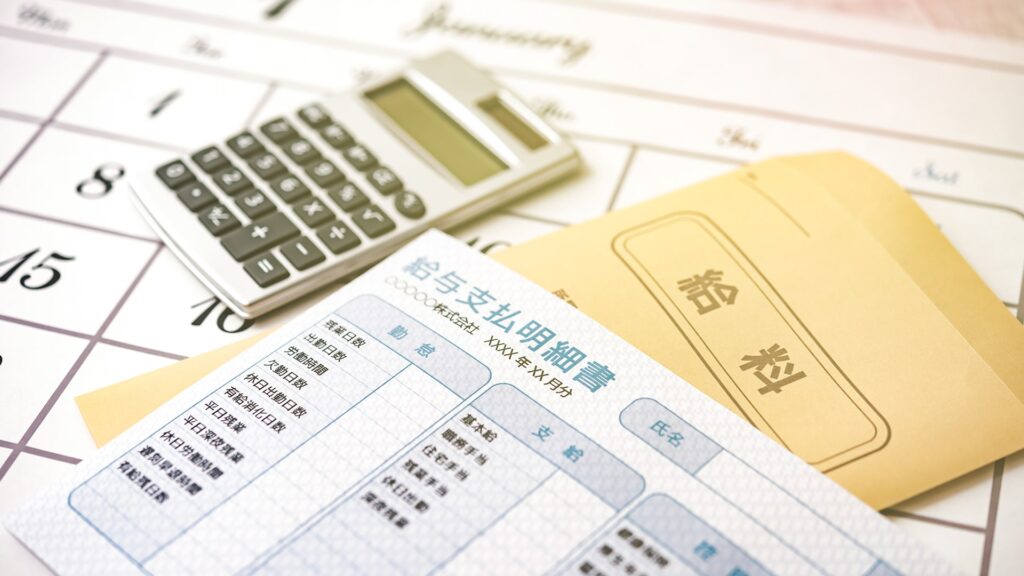

特に近年は、時代の流れもあり、働き方改革や育児・介護に関する制度の変化が頻発しています。
これにより、企業側が正しく把握しきれず、知らず知らずのうちに違反してしまうケースも増えています。
そのため、給与計算は「単なる事務作業」ではなく、経営リスクを左右する重要な労務管理のひとつといえます。
こうした給与計算ミスによるリスクを防ぐには、専門知識をもつ社労士のサポートが非常に有効です。
給与計算ミスによる具体的なトラブル例
● 残業代の計算ミスで労働基準監督署から指摘
計算方法が誤っており、「未払いがある」と労働基準監督署から指摘され対応せざるを得ない状況になった、その結果、従業員からの信頼が揺らいでしまった。
● 住民税の金額を誤って控除し、本人が気づいたことで不信感が広がった
自治体からの通知を正確に反映できておらず、従業員の自己負担が一時的に増えた。
管理がずさん、との声が上がった。
● 社会保険の加入・喪失時期のズレによる二重控除
加入時の一例:本来社会保険に加入すべき従業員の手続きを勘違いにより手続きしておらず、後日気づいて遡って手続きをした。そのことにより保険料を給与から数か月分天引きすることになり、負担が大きすぎる、なぜ最初から適切に手続きをしていなかったのか、と言われた。
● 賞与にかかる社会保険料の控除ミス
控除漏れが後から発覚し、会社が全額を負担して支払うことに。思わぬ追加コストが発生した。
● 育休中の保険料を誤って控除
本来は免除対象であるにも関わらず、育児休業中の従業員の社会保険料を控除してしまい、訂正・返金の対応に追われた。

上記のような給与計算のトラブルは、実は珍しいものではありません。
そして、そのような出来事をきっかけに「やはり専門家にお願いしよう」とご相談をいただくケースも多くあります。
従業員の方にとって、給与は生活を支える大切な基盤です。
「正しく、きちんと支払われること」は、当然のことのように思えますが、
だからこそ、たった一度のミスでも信頼を損ねてしまうことがあります。
もちろん、企業様も決して故意に間違えるわけではありません。
給与計算には、労働基準法や社会保険・労働保険など、複雑な法律が関わっています。
しかも、法律や運用ルールが一時的に変わることもあります。
「知らなかった」「うっかりしていた」では済まされないことも少なくありません。
実際に、企業のご担当者様からはよく
「きちんと給与ソフトを使っていたのに、なぜ間違いが起きてしまったのか…」というお声をお聞きします。
確かに、ソフトはとても便利なツールですが、最終的に設定や判断を行うのは「人」です。
正しい知識と経験がなければ、どんなに優れたシステムを使っていても、正確な給与計算にはつながりません。
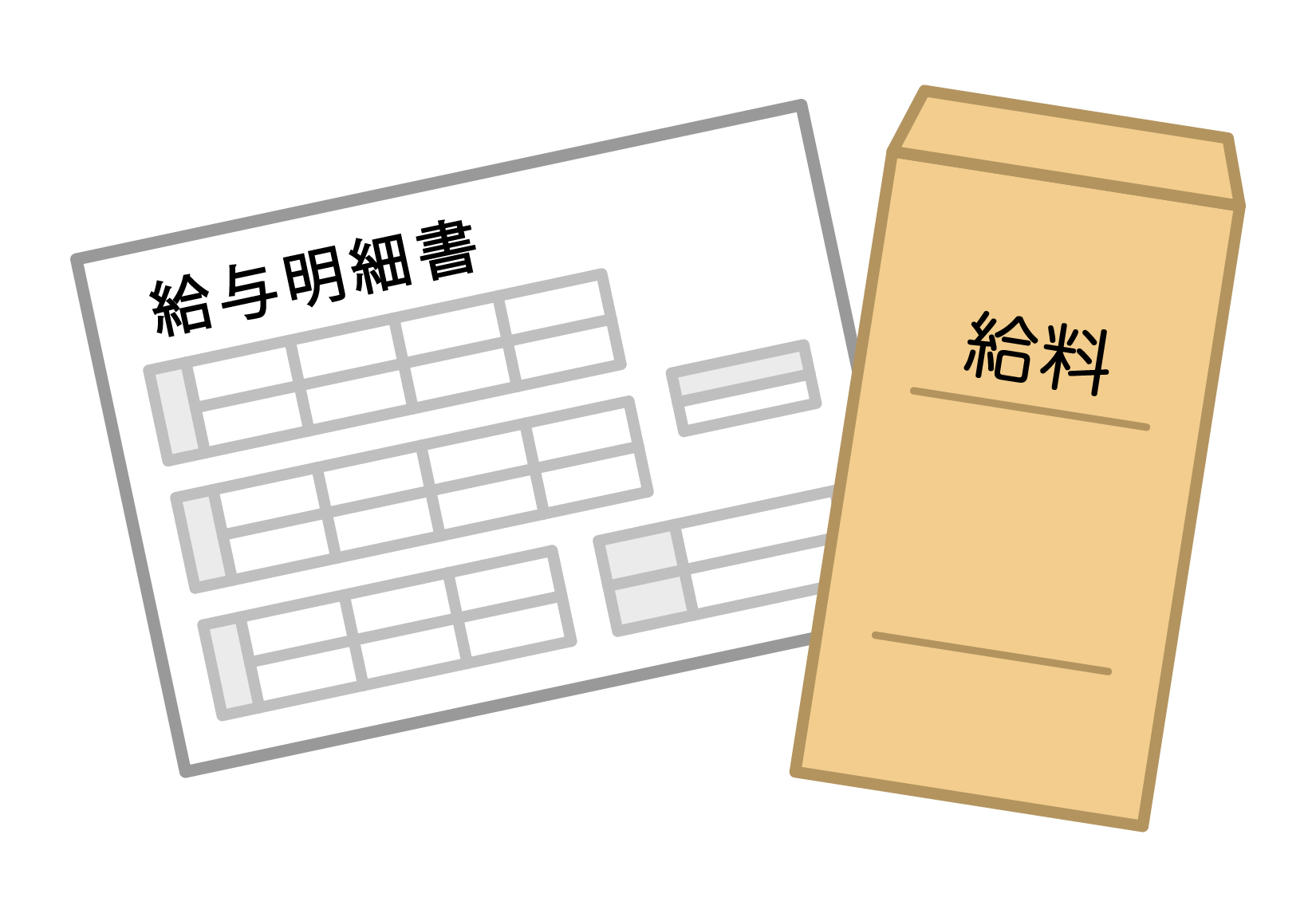

給与計算導入までの流れ(一例です)
過去の賃金台帳や就業規則(賃金規程等)を受領し確認
従業員情報の収集
(扶養控除申告書・住民税の特別徴収税額決定通知書等受領、社会保険の等級確認、給与金額の確認等)
法令通りできているか、是正する箇所が無いかなどのチェック
打ち合わせにて今後の方針を決定
※導入までの期間については、従業員数等の状況により企業ごとに異なります。
詳細はお問い合わせください。
お問い合わせ
CONTACT